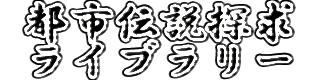内輪ネタから始まったクトゥルフ神話
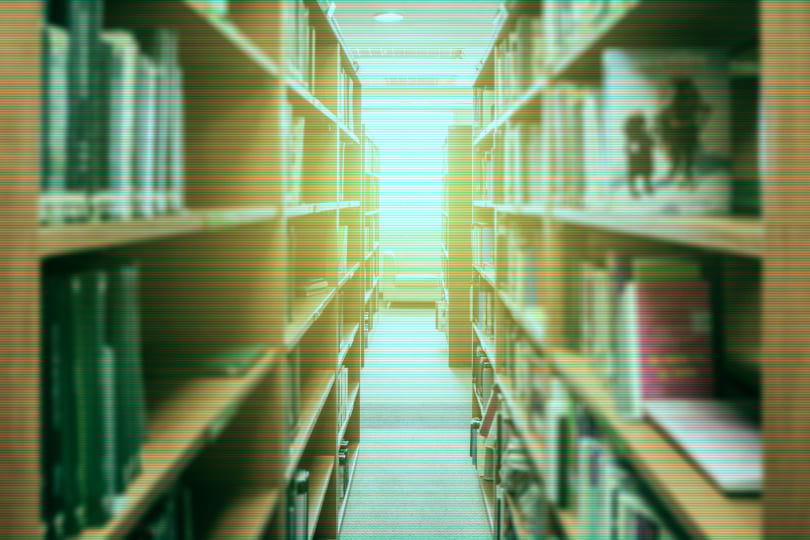
架空の神々と宇宙的恐怖を描く「クトゥルフ神話」。いまやTRPGやアニメなどでも親しまれるこの神話体系は、実はとても意外な成り立ちをもっている。この記事では、クトゥルフ神話の起源と日本での受け入れられ方に迫る。
クトゥルフ神話とは
クトゥルフ神話は、アメリカの作家H.P.ラヴクラフトが1920年代に発表した一連のホラー作品を起点として、後続の作家たちが独自に世界観を広げていった創作神話である。ラヴクラフトの代表作『クトゥルフの呼び声』を筆頭に、神話に登場する神々や書物、地名などが共通要素として用いられ、他の作家たちの作品にも織り込まれていった。
創作仲間との文通から始まった神話体系
当初、クトゥルフ神話はラヴクラフトとその創作仲間との間で交わされた内輪ネタに過ぎなかった。彼らは互いの作品に登場するキャラクターや設定を共有し、物語の世界を広げていくことを楽しんでいた。その後、ラヴクラフトの死後、彼の友人である作家オーガスト・ダーレスがその作品群を体系化し、「クトゥルフ神話」として名付けたのである。
恐怖の概念を塗り替えた“宇宙的恐怖”
ラヴクラフトが描いた恐怖は、それまでの吸血鬼や幽霊といった怪異とは一線を画していた。彼は人知を超えた存在、つまり人間の価値観や倫理がまったく通じない“宇宙的恐怖(コズミック・ホラー)”を創造し、それに対する人間の無力さを描いた。クトゥルフ神話に登場する神々は、単なる脅威ではなく、人間の理解を遥かに超える存在なのだ。
日本人にとってのクトゥルフ神話
クトゥルフ神話は、日本においても独自の進化を遂げている。この神話世界が、どのようにして日本文化の中に受け入れられ、親しまれていったのかを見てみよう。
江戸川乱歩が最初の紹介者
日本にクトゥルフ神話を紹介した最初の人物は、探偵小説の巨匠・江戸川乱歩だとされている。1948年、彼は雑誌「宝石」の中でラヴクラフトの作品に触れ、次元を超えた異世界的恐怖に言及した。乱歩の熱量ある紹介により、日本の読者もこの神話世界に関心を持ち始めた。
“萌え”文化との融合
クトゥルフ神話は、2000年代以降、日本のポップカルチャーと融合し始める。代表的なのが『這いよれ!ニャル子さん』といった作品で、恐怖の神々が美少女キャラとして登場し、新たな魅力を放った。神々が“キャラ化”されることで、神話が持っていたおどろおどろしさは和らぎ、若年層にも広く浸透することになった。
神への認識が異なる日本人の感性
西洋では“神=絶対的存在”として描かれることが多いが、日本人にとっての神は“身近な自然の象徴”や“助けてくれる存在”であることが多い。そのため、クトゥルフのような存在も「恐ろしいけれど、どこか魅力的」と受け入れられやすかったのかもしれない。恐怖の対象でありながらも、親しみをもって語られるのは、こうした文化的背景が影響していると考えられる。
今も拡張し続けるクトゥルフ神話
ラヴクラフトの没後も、クトゥルフ神話は世界中のクリエイターたちによって語り継がれている。日本でもTRPGや小説、アニメといったさまざまな形で進化を遂げ、今や「共有できる世界観」として定着している。かつては内輪ネタだった物語が、いまやグローバルな文化遺産へと成長しているのだ。