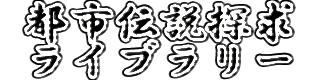『口裂け女』の真実とは?日本全国に広がった怪談の起源

1970年代後半、突如として日本中の子どもたちを震え上がらせた「口裂け女」。その存在は今や怪談界の定番とも言えるが、果たして彼女は本当に“怪物”だったのか? この記事では、口裂け女の原点から、その後の変容、社会的な背景までを掘り下げていく。
1970年代に日本各地で流行した都市伝説
1979年、日本の各地で「口裂け女が現れた」という噂が爆発的に広がった。赤いコートにマスク姿、そして「私、キレイ?」という問いかけの後、マスクを外して裂けた口元を見せる――そんな描写が多くの子どもたちの間で語られ、恐怖の対象となった。
だが実際には、この都市伝説には1970年代半ばからすでに複数のバージョンが存在していたとされる。地方紙や深夜ラジオ、子ども同士の噂などを通じて、じわじわと全国へと広がっていったのだ。その時点では、口裂け女は幽霊でも妖怪でもなく、どこかの町に現れた“おかしな人間”というリアルな存在として語られていた。
この点こそ、当時の都市伝説としての新しさだった。ありえない怪物の話ではなく、「本当にいるかもしれない人間の怖さ」。今で言う“ヒトコワ”的な要素が、子どもたちにリアルな恐怖を植えつけたのだ。
変化していった口裂け女
この噂に劇的な変化が訪れるのは、1979年以降。全国紙やテレビ番組、週刊誌などのマスメディアが口裂け女の存在に注目し、特集や記事として取り上げ始めたことで、噂は一気に“全国共通の怪談”へと変貌した。
これにより、口裂け女は“ただのイタズラ”から“超自然的存在”へとシフトしていく。たとえば、もともとは「口紅で裂けた口をメイクした女装の男だった」という話も存在していたが、マスコミによって広まった後は、異様に高い身長や高速移動、鎌を持っているといった“怪物化”が進んでいった。
背景には、戦前に流行した「赤マント」や、70年代に語られていた「カシマ」怪談の影響もあったのではないかと考えられている。どちらも“赤い服の女性”や“顔に傷を負った女性”といった共通点を持ち、都市伝説が時代や媒体を通じて融合・変化していく様子が見て取れる。
つまり、口裂け女は当初「人間らしい怖さ」を持った都市伝説であり、時代と共に「怪異としての怖さ」へと進化していったのである。
マスコミがリアリティを奪った瞬間
本来、「自分たちの町だけの話」として広がったからこそリアリティがあった口裂け女。しかし、それが全国に知れ渡ったことで、「ありえる話」から「作られた話」へと変化してしまった。この変化は、怪談が“信じられるから怖い”という本質を見失わせる転機でもあった。
今も残る「口裂け女」の痕跡
現在でもネットやSNS上で語られる怪談の中に、口裂け女の要素が影響を与えているケースは多い。都市伝説はただの噂話ではなく、時代の空気や社会不安を反映した“現代の民話”なのかもしれない。
怪談の原点に立ち返るとき
口裂け女という存在を振り返ると、それは「人間が最も怖い」という根源的な恐怖を映し出した鏡だったのかもしれない。そして、それが“作られた怪物”へと変貌していく過程には、現代社会の情報伝播の在り方も浮かび上がってくる。今こそ、怪談の原点に立ち返って、なぜ人は語り、恐れるのかを再考する時なのではないだろうか。